











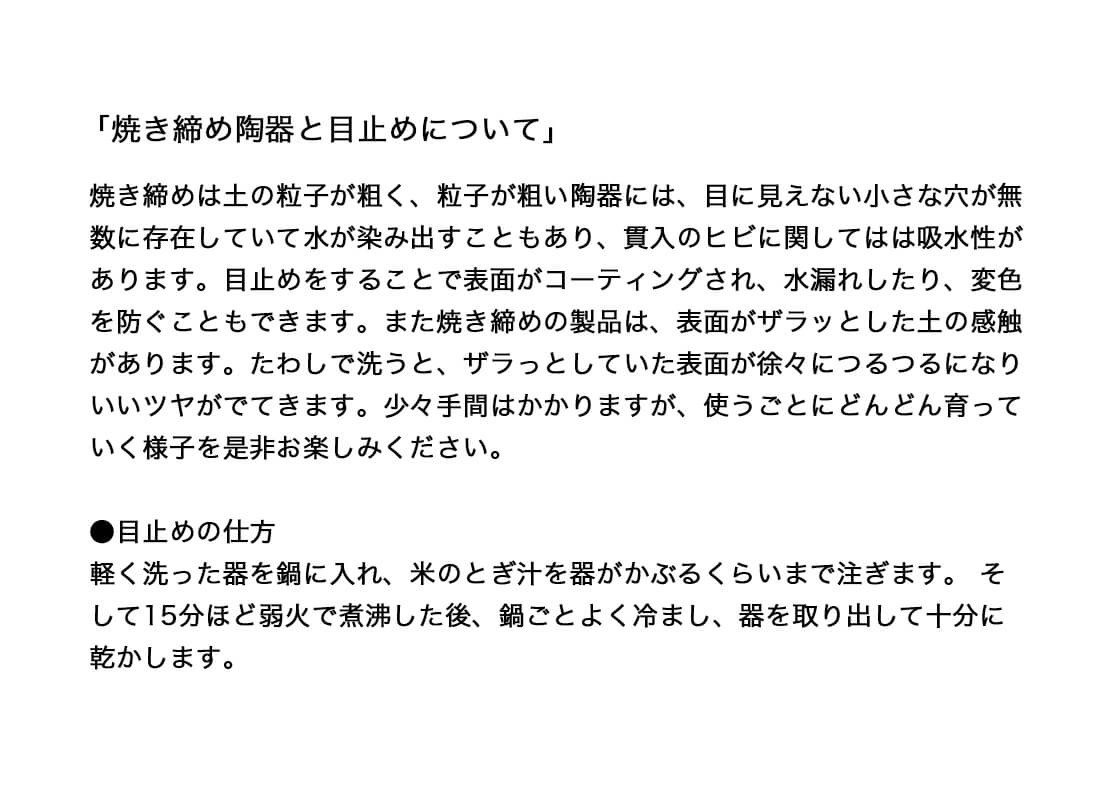
日本六古窯の一つに数えられる「丹波焼」の真骨頂、登り窯で焼成された丹文窯の焼き締め豆皿(深)のご紹介。
登り窯でしか表現できない混じりけやブレ、錆びた様な風合いは荒々しくも自然な美しさを持った味わい深い作品です。
丹波焼は、瀬戸、常滑(とこなめ)、信楽(しがらき)、備前、越前とともに日本六古窯の一つに数えられ、その発祥は平安時代末期から鎌倉時代の初めといわれています。
桃山時代までは「穴窯」が使用されていましたが、慶長16年(1611)ごろ朝鮮式半地上の「登り窯」が導入され同時期に取り入れられた蹴りロクロ(日本では珍しい立杭独特の左回転ロクロ)とともに、伝統技術を今日に受け継いでいます。
登り窯で焼成される焼締めは丹波焼の真骨頂で人工的な釉薬(ゆうやく)は使われていません。
窯の中で長時間焼かれることにより、燃えた薪の灰が焼成中に器に降りかかって、原土の中に含まれた鉄分と融け合い、緑色や鳶(とび)色を自然発色。
これが自然釉(ビードロ釉)といわれるもので、穴窯時代の丹波焼の特徴となっています。
現代ではこの焼締めの他に自然の釉薬を施し、登り窯やガス窯で食器・酒器・花器などを中心に生産されており、日本を代表する陶器の産地として名を馳せています。
名称については、穴窯時代は小野原焼、登り窯時代になってからは、「丹波焼」または「立杭焼」と呼ばれてきました。
現在では組合で「丹波焼」に統一されていますが昭和53年(1978)「丹波立杭焼」の名称で国の伝統的工芸品指定を受けています。
丹文窯(たんぶんがま)
丹文窯は丹波焼の数ある窯元の中でも代々続いている窯元です。現在では60軒以上ある丹波焼の窯元ですが、初代の頃はまだ20、30軒しかなく、立杭の中でも歴史のある窯元。当時は酒樽を中心に作り灘の酒蔵に卸していましたが、今は広く一般にも使えるような和食器、民芸を中心に製作されています。丹波焼の窯元の中でも登り窯の作品が多く、独創的な作品が多いのも特徴です。
コチラは丹文窯で生み出される、丹波焼の真骨頂、登り窯で焼成された焼き締めによる深めの豆皿。
焼き締めは釉薬を用いず、登り窯を使用して1100~1300℃の高温で長時間焼きます。
この窯の中で焼いている最中に、自然とかかる灰などが自然釉となり、自然な色や模様が入ります。
また、素地に含まれる鉄分が酸化することで赤褐色に発色する緋色、灰が器に降りかかって黒く焼き付く豪快な見た目の灰被りなど、土の性質と炎の力が生み出す自然の焼き目により二つとない個性的な陶器に仕上がるわけです。
直径7~8cm前後の土手のある深めの豆皿。
やや深さがあるので、漬物や乾物だけでなく汁気のある総菜を盛るのにもご使用いただけます。
豆皿は、少ない量の盛り付けで済むので、ストックしているお野菜、漬物や残りもののおかずをちょこちょこと並べるだけで、食卓の見た目が華やかになり、食事の満足度も高くなります。
これぞ丹波焼とも言える豪快さで荒々しさのある焼き締めの器。
手間のかかる工程や焼き時間の長さ故に大量生産に不向きな面も持ち合わせており、こちらの豆皿も正に一期一会の製品となっております。
是非ご検討ください。
「焼き締め陶器と目止めについて」
焼き締めは土の粒子が粗く、粒子が粗い陶器には、目に見えない小さな穴が無数に存在していて水が染み出すこともあり、貫入のヒビに関してはは吸水性があります。目止めをすることで表面がコーティングされ、水漏れしたり、変色を防ぐこともできます。また焼き締めの製品は、表面がザラッとした土の感触があります。たわしで洗うと、ザラっとしていた表面が徐々につるつるになりいいツヤがでてきます。少々手間はかかりますが、使うごとにどんどん育っていく様子を是非お楽しみください。
※目止めの仕方
軽く洗った器を鍋に入れ、米のとぎ汁を器がかぶるくらいまで注ぎます。 そして15分ほど弱火で煮沸した後、鍋ごとよく冷まし、器を取り出して十分に乾かします。
◆実寸サイズ
(FREE)/直径(上部)約7cm~8cm/直径(底面)約3cm~4cm/高さ約2cm
※生産の特性上、サイズ・形に誤差がございますので採寸値は目安とお考え下さい。
◆素材:陶器
◆カラー展開:グレー系、ベージュ系、アイボリー系
◆生産国:日本













